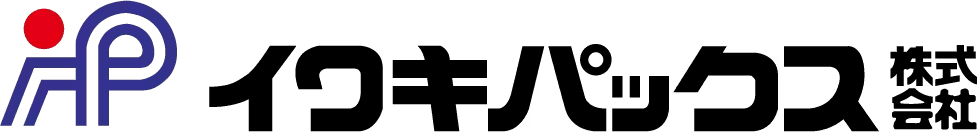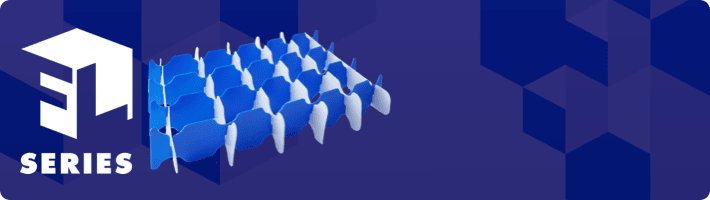共同輸配送(共同配送・共同物流)とは
物流の共同輸配送(共同配送・共同物流)とは
近年、個別企業で担っていた物流機能を、他社と共同することで限られた経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)を補い合い有効活用する動きがあります。一般的に物流効率化の投資負担は大きく、複数の企業が共同で投資を行うと効率が良くなり、1社あたりの負担が減ります。
輸配送の共同化は以下のような問題を解決するのに有効です。
①人材不足などの問題
②交通渋滞や大気汚染などの問題
③投資時の資金調達の問題
共同輸配送の種類や、共同輸配送に関連する言葉について紹介します。
①集荷・配送の共同化(輸配送の共同化)
集荷や配送を共同することで、1回に輸送する数量を多くでき、帰り便を有効活用でき、交錯輸送(※1)を回避できます。

(※1 : 交錯輸送とは、複数の拠点に在庫されているアイテムがそれぞれ別便で同じ場所へ輸送されることを言います。)
②物流センターを共同して設置(物流拠点の共同化)
物流拠点を共同して設置、集荷・配送のみならず、保管・ (※2)・仕分けを他社と共同することで効率化できます。

(※2 : 流通加工とは物流拠点で商品を加工し、付加価値を上げる作業です。具体的には大きな入れ物から小さな入れ物へ詰め替える小分け作業、名札や値札などのタグ付け、商品へのラベル貼り、個々の商品をセットにする作業などがあります。顧客側が行うべき作業をサービスとして無償で行うことがありました。)
③共同物流の情報ネットワークを構築(情報システムの共同化)
受発注デ-タや在庫デ-タを統合したシステムをネットワーク化することにより、在庫を適正化し、また、変化する状況に応じた効率が良い配送・納品ができるようになります。
「共同輸配送や帰り荷確保等のためのデータ連携促進支援事業費補助金」について
国土交通省ではWEBサイトで下記のように告知されています。
本事業は、「物流情報標準ガイドライン」を活用して共同輸配送や帰り荷の確保、配車・運行管理の高度化等の物流効率化を図るために、複数の荷主企業や物流事業者、物流ソリューション提供者(物流マッチングサービス等)が連携して「物流・商流情報のオープンプラットフォーム」の構築や運営を行う取り組みに対して効率的に支援することを目的としています。事業に要する経費の一部を補助する事業に補助金を交付することにより、物流データの標準化を推進し、物流DXや新たな物流ソリューションを促進するものです。

このような補助金が続く場合があるので、関係する方は国土交通省のWEBサイトを定期的にチェックすると良いと思います。
物流センターでの仕分けで通い箱や内装材(仕切り、緩衝材)が必要なとき
物流センターの仕分けにはオリコンなどの通い箱や内装材(仕切り、緩衝材)が必要になることがあります。オリコンは既製品ですので、発注から納品までの調達リードタイムが比較的短いですが、内装材(仕切り、緩衝材)は受注生産で製作することが多く、生産リードタイムが比較的長いので注意が必要です。
お問い合わせ
お問い合わせは以下のフォームからお願いいたします。